将棋界において「永世竜王」は、特別な意味を持つ永世称号のひとつです。その称号を得るには厳しい条件を満たす必要があり、まさに限られた棋士だけに許される名誉といえます。永世竜王という偉業を達成した棋士は、将棋界の歴史に名を刻む存在となります。
今回は、将棋の永世竜王になるための達成条件の詳細をはじめ、永世称号の意義やメリット、さらに将棋界でその称号を保持する歴代保持者たちの功績について解説していきます。
特に、藤井聡太さんが今後この称号を目指す可能性にも触れ、永世竜王が持つ価値と魅力を深掘りしていきます。また、羽生善治さんや渡辺明さんといった歴代の保持者についても取り上げ、彼らの達成の背景や将棋界への影響も紹介します。
将棋の永世竜王の達成条件と位置づけ
将棋界において最も格式の高いタイトル戦の一つである「竜王戦」。その中でも、特別な条件を満たした棋士に与えられるのが「永世竜王」という称号です。ここでは、永世竜王とはどのような存在なのか、その条件や将棋界における位置づけについて詳しく見ていきます。
将棋の永世竜王とは何か
永世竜王とは、将棋界において非常に栄誉ある称号の一つであり、竜王戦という最高峰のタイトル戦において、特定の条件を満たした棋士にのみ与えられる「名誉称号」です。この永世称号は現役・引退を問わず棋士の功績として永久に残り、名誉ある勲章のようなものといえるでしょう。
そもそも「竜王」は将棋界で最も賞金額が高く、格式あるタイトル戦であり、毎年行われる竜王戦を制した棋士が1年間「竜王」を名乗ることができます。その中で、ある一定回数この竜王位を獲得した棋士にだけ「永世竜王」の称号が与えられます。
この称号は、将棋ファンだけでなく将棋界全体からも高い評価を受けており、達成者はまさに“伝説的存在”として語り継がれる存在です。称号そのものが持つ重みが、永世竜王の希少性と価値を物語っています。
将棋の永世竜王の達成条件とは
永世竜王の称号を得るためには、単に竜王位を一度獲得するだけでは足りません。具体的には、「通算7期」または「連続5期」のいずれかを達成することが条件とされています。
通算7期とは、竜王位を通算で7回獲得することであり、必ずしも連続していなくても構いません。一方の連続5期は、5年連続で竜王位を防衛・奪取するという極めて困難な偉業を意味します。
このような条件を満たすには、実力はもちろん、長期にわたる安定した成績と精神力が求められます。多くの強豪棋士でもそう簡単には到達できない難関であり、だからこそ「永世竜王」は特別な存在なのです。
「通算7期」または「連続5期」獲得
将棋の永世竜王のメリットと意義
将棋界で永世竜王の称号を得ることは、棋士個人にとって計り知れない名誉です。まず第一に、「永世」の名が示す通り、その称号は生涯にわたって保持され続け、引退後も公式プロフィールなどに明記されます。つまり、実績として一生認められる名誉ある勲章なのです。
また、将棋界におけるブランド価値も飛躍的に高まります。対局料やメディア露出の増加、将棋イベントへの招待など、永世称号を持つ棋士には多方面からの注目が集まります。特に若い世代や将棋ファンにとっては「憧れの存在」として、後進のモチベーションにもつながるでしょう。
さらに、将棋史に名前を刻むという意味でも大きな意義があります。永世竜王は非常に限られた棋士しか達成していないため、その存在自体が伝説として語り継がれ、棋士としての格を確立する象徴ともなります。
将棋の永世竜王の歴代保持者一覧とその軌跡
永世竜王という称号を実際に手にした棋士は、将棋の歴史の中でもごくわずかしか存在しません。ここでは、これまでに永世竜王の称号を獲得した歴代保持者とその達成までの軌跡をたどりながら、永世竜王たちの偉大な実績とその背景に迫っていきます。
将棋の永世竜王の歴代保持者一覧
永世竜王の称号は、長年にわたる実力と安定した成績を証明する勲章であり、その称号を得た棋士は非常に限られています。将棋界の歴史の中で、永世竜王の称号を正式に保持しているのは次の3名です。
永世竜王の歴代保持者一覧
- 渡辺明:連続5期&通算7期
- 羽生善治:通算7期
- 藤井聡太:連続5期
※2025年11月13日時点
初代永世竜王である渡辺明さんは、竜王戦での安定した強さを誇り、長年にわたりトップ棋士として活躍してきました。
一方の羽生善治さんは、竜王戦以外にも多数の永世称号を持つ「永世七冠」としても知られており、将棋界のレジェンド的存在です。
そして藤井聡太さんは「八冠」も達成した現在最強の棋士です。
この3人の棋士は、ただ単に強いだけでなく、時代を代表する存在として将棋の普及や文化的価値の向上にも寄与してきました。永世竜王の称号は、そのような功績を裏付ける象徴とも言えるのです。
渡辺明の永世竜王達成
渡辺明さんは、将棋界において「竜王戦の申し子」ともいえるほど、竜王戦に強い棋士として知られています。2004年からの5連覇で永世竜王の資格を獲得しましたが、特に永世竜王の資格がかかった2008年の竜王戦七番勝負は挑戦者の羽生善治さんも通算7期目の竜王位がかかっており、”100年に1度の大勝負”として語り継がれる竜王戦史上でも極めて異例の名勝負となりました。
若くして頭角を現した渡辺明さんは、冷静な読みと大胆な指し回しを兼ね備えたスタイルで、同世代の棋士たちの中でも突出した実績を築いてきました。特に竜王戦では圧倒的な集中力と勝負強さを見せ、決勝トーナメントを勝ち上がってきた羽生世代を中心とした挑戦者を毎年のように退けたことは将棋ファンの記憶にも強く残っています。
また、渡辺明さんは永世竜王達成後もトップ棋士として活躍を続けており、名人位など他のタイトル戦にも挑み続けています。その実力とキャリアは将棋界に多大な影響を与えており、羽生善治さんと並んで現代将棋を象徴する存在と言っても過言ではありません。
羽生善治と永世竜王
羽生善治さんは、永世竜王の称号を持つ棋士として最も有名な存在の一人です。彼は1990年代から2000年代にかけて、数多くのタイトルを獲得し、将棋界を席巻しました。その中でも竜王位は特に重要なタイトルであり、羽生善治さんは2017年に通算7期の竜王位獲得によって永世竜王の資格を得ました。
羽生善治さんの凄さは、単なるタイトル数の多さだけではありません。彼は当時すべてのタイトルで永世称号を取得可能な条件を満たした「永世七冠」の達成者であり、まさに前人未踏の記録を打ち立てています。その中での永世竜王は、彼のキャリアの中でも特に象徴的な称号です。
また、羽生善治さんはは将棋の普及にも積極的に関わっており、メディア出演や著書の執筆、講演などを通じて広く社会に影響を与えています。彼の存在そのものが、永世竜王という称号の重みを一層引き立てているといえるでしょう。
将棋の永世竜王達成者の共通点と歴代比較
これまでに将棋の永世竜王の称号を得た棋士にはいくつかの共通点があります。それは、「長期間にわたる安定した成績」「終盤力の高さ」「大舞台での勝負強さ」、そして「時代の中心にいた存在感」です。
羽生善治さんはあらゆるタイトルを制した万能型の棋士であり、どんな局面でも勝機を見出す直感力と読みの深さに長けていました。一方、渡辺明さんは冷静な判断と計算された戦略で盤面を支配し、頭脳的な勝負を得意としています。スタイルは異なれど、どちらも竜王戦という大舞台で何度も結果を出しているのが特徴です。
こうした実績を比較することで見えてくるのは、「永世竜王に求められるのは単なる強さだけでなく、精神的な安定と勝負に対する執念」であるという点です。今後この称号に名を刻む棋士が現れたとき、また新たな共通点や傾向が浮かび上がるかもしれません。
藤井聡太が目指す永世竜王への道
将棋界の新時代を象徴する存在、藤井聡太さんは、すでに数々のタイトルを獲得し、前人未到の領域に近づきつつあります。2023年に全8タイトルを同時制覇したことで話題となりましたが、その中に含まれているのが「竜王」の称号です。つまり、藤井聡太さんもすでに永世竜王への第一歩を踏み出しているということになります。
永世竜王の条件である「通算7期」または「連続5期」のいずれかを今後達成することで、藤井聡太さんはこの称号を手にする可能性があります。現在の年齢や勢い、圧倒的な勝率を考慮すれば、その可能性は非常に高いと言えるでしょう。
ただし、竜王戦は将棋界で最も賞金が高く、挑戦者のレベルも極めて高い戦いです。若くして八冠を達成したとはいえ、これから安定的に勝ち続けることが求められます。その意味で、藤井聡太さんが永世竜王を達成する過程は、今後の将棋界最大の注目ポイントの一つと言えるでしょう。
追記:2025年11月13日、藤井聡太さんは竜王位連続5期獲得により、史上3人目の永世竜王の資格者となりました。
こちらの記事も合わせてどうぞ↓↓
将棋の歴代竜王一覧
竜王戦は1988年に創設されて以来、数々の名勝負と名棋士を生み出してきました。ここでは、歴代の竜王保持者を一覧で紹介し、それぞれの時代を彩った棋士たちの歩みを振り返ります。
将棋の歴代竜王一覧は以下の通りです。
将棋の歴代竜王一覧
1988年 島朗
1989年 羽生善治
1990・1991年 谷川浩司
1992年 羽生善治
1993年 佐藤康光
1994・1995年 羽生善治
1996・1997年 谷川浩司
1998~2000年 藤井猛
2001・2002年 羽生善治
2003年 森内俊之
2004~2012年 渡辺明
2013年 森内俊之
2014年 糸谷哲郎
2015・2016年 渡辺明
2017年 羽生善治
2018年 広瀬章人
2019・2020年 豊島将之
2021年~ 藤井聡太
こちらの記事も合わせてどうぞ↓↓
将棋の永世竜王になる達成条件と歴代保持者一覧~まとめ
今回は、将棋の永世竜王になるための達成条件の詳細をはじめ、永世称号の意義やメリット、さらに将棋界でその称号を保持する歴代保持者たちの功績について見てきました。
将棋界で最も権威ある称号の一つとされる「永世竜王」の達成条件は、竜王位を通算7期、もしくは連続5期獲得した棋士に贈られる名誉ある永世称号です。永世竜王の称号は現役・引退を問わず生涯にわたって保持され、棋士としての格や実績を象徴するものとなります。その価値は極めて高く、棋士本人のブランド力を高めるとともに、将棋界全体に与える影響も大きいといえるでしょう。将棋ファンの間でも特別な称号として語り継がれており、「伝説」として扱われることも珍しくありません。
永世竜王の称号をこれまでに手にした棋士は、羽生善治さんと渡辺明さん、藤井聡太さんの3名のみです。渡辺明さんは連続5期と通算7期の両方を達成しており、初代永世竜王としてその地位を確立しました。一方、羽生善治さんは通算7期の獲得により永世竜王の資格を得ており、永世七冠の達成者としても将棋史に名を残しています。そして藤井聡太さんは「八冠」も達成した現在最強の棋士といえます。3人に共通するのは、長期間にわたる安定した成績、大舞台での勝負強さ、そして将棋界の中心に立ち続けてきた存在感です。
また、1988年から続く竜王戦の歴代保持者を見渡すことで、時代ごとのトップ棋士の系譜が浮かび上がります。竜王戦の歴史は、まさに将棋界の進化と競争の記録でもあり、それぞれの時代に名を馳せた棋士たちの努力と栄光を物語っています。
将棋の世界で永世称号を得るということは、単なる強さではなく、継続的な結果と信頼の証です。永世竜王という称号は、今もそしてこれからも、将棋界で最高の名誉のひとつとして語り継がれていくことでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



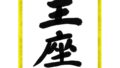
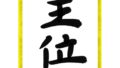
コメント
>そして藤井聡太さんは「永世八冠」も達成した現在最強の棋士です。
えっ?
失礼しました。
「永世八冠」→「八冠」の間違いです。
訂正しました。
ご指摘ありがとうございました。